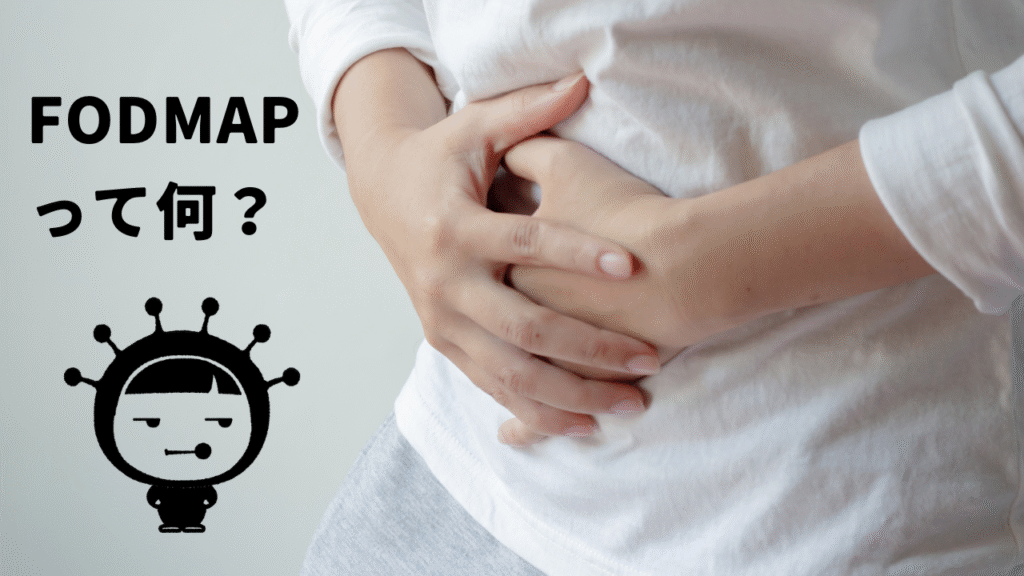
健康を意識して、食事に糀や甘酒を取り入れる。 体に良いと信じていた発酵食品なのに、なぜかお腹が張ったり、ゴロゴロと不快感があったり…。
もし、そんな経験に心当たりがある方がいらっしゃいましたら、この記事を読んでみてくださいね。
以前、とある商談で糀シロップのサンプルをお持ちした時のことです。ありがたいことに相手方のスタッフさん達にコージローは好評でした。
しかしスタッフさんの一人だけが試食に手を伸ばしていただけない。
「もしかして糀が苦手ですか?
糀が苦手な方が楽しめるように設計していますので、よかったら少しだけでも試してみてくださいね」
と声をかけてみたところ、その方は
「本当は糀が大好きですごく食べてみたいのですが、私はフォドマップ体質で…。食べるとすぐにお腹が張ってしまうんです」とおっしゃいました。
正直なところ、私はその時まで「FODMAP」という言葉を詳しく知りませんでした。 大好きだと言ってくれる方に、商品を届けられないことがある。私はとても驚きました。
この出来事をきっかけに、私はFODMAPについて知ることになりました。 今回は、原因の分からないお腹の不調に悩む方のために、FODMAPについて、そして私の製品との関わりについて、正直にお話ししたいと思います。
FODMAP(フォドマップ)とは何でしょうか?
少し聞き慣れない言葉かもしれませんね。
FODMAPとは、 Fermentable(発酵性の) Oligosaccharides(オリゴ糖) Disaccharides(二糖類) Monosaccharides(単糖類) And Polyols(ポリオール類)
これらの頭文字をとった言葉です。これらはすべて、食品に含まれる糖質の種類を指しています。
ここで大切なのが、最初の「F(発酵性)」という言葉です。 これは、食品自体が「発酵食品」であるという意味とは少し違います。FODMAPの「F」は、その食品に含まれる糖質が、「あなたの大腸の中で」腸内細菌によってエサとなり、発酵させられる、という意味なのです。
つまりFODMAPとは、一言でいうと「小腸で消化しきれず、大腸でガスを発生させやすい糖質」たちのこと。体質によっては、このガスがお腹の張りやゴロゴロとした不快感、痛みの直接的な原因になるのです。
では、このような体質の方はどのくらいいるのでしょうか。 FODMAPに過敏な方の正確な統計はまだありませんが、関連の深い「過敏性腸症候群(IBS)」は、日本人の約10%〜15%、つまり10人に1人程度が当てはまると言われています。決して珍しいことではなく、多くの方が同じように悩んでいます。
そして、FODMAPへの反応は、アレルギーのように人それぞれです。ある特定の糖質のグループにだけ反応する方もいれば、複数のグループに反応する方もいます。どの食品で、どのくらいの量で不調を感じるかは、本当に千差万別なのです。
もし「コージロー」で不調を感じたら
もし「コージロー」を飲んで、お腹の張りなどを感じる場合、それは原料である米糀に含まれる「オリゴ糖(Oligosaccharides)」というグループのFODMAPに、あなたの体が反応しているサインかもしれません。
「オリゴ糖」と聞いても、あまりピンとこないかもしれませんね。 実は、一見すると無関係に思える、以下のような食品も同じグループの仲間なのです。
もし「コージロー」で不調を感じる方は、これらの食品を食べた時にも、似たような経験をされている可能性があります。
<「オリゴ糖」を多く含む食品の例>
- 小麦製品(パン、うどん、パスタなど)
- 一部の野菜(玉ねぎ、にんにく、ねぎ、ごぼうなど)
- 大豆製品(納豆、豆腐、豆乳など)
「こんなにたくさんの種類があるの?」と驚かれたかもしれません。
お腹の不調を感じやすい方が、普段からなんとなく避けている食品と多く重なるのではないでしょうか。
FODMAPの考え方が興味深いのは、これらの不調の原因を「消化が悪いから」と一括りにするのではなく、「特定の糖質(この場合はオリゴ糖)への不耐性」という、より具体的な視点で捉える点にあります。
もし、特に小麦製品や玉ねぎを食べた時に強く不調を感じる、あるいは大豆製品を食べた時だけ不調を感じる、など、ご自身の傾向に心当たりがあれば、それはFODMAPのタイプを見つける大きなヒントになります。
「コージロー」も、残念ながら、すべての方の体質に合う万能な食品ではありません。
もし、この記事を読んでご自身の経験と重なる点があれば、ぜひ一度「FODMAP」という視点を意識して、日々の食事と体調の変化を観察してみてください。
体に合わない食べ物を知ることは、決して残念なことではありません。 それは、ご自身に本当に合った、心地の良い食生活を見つけるための大切な一歩です。
この記事が、そのためのきっかけになれば幸いです。
(※不調が続く場合は、自己判断せず専門の医療機関にご相談ください。)