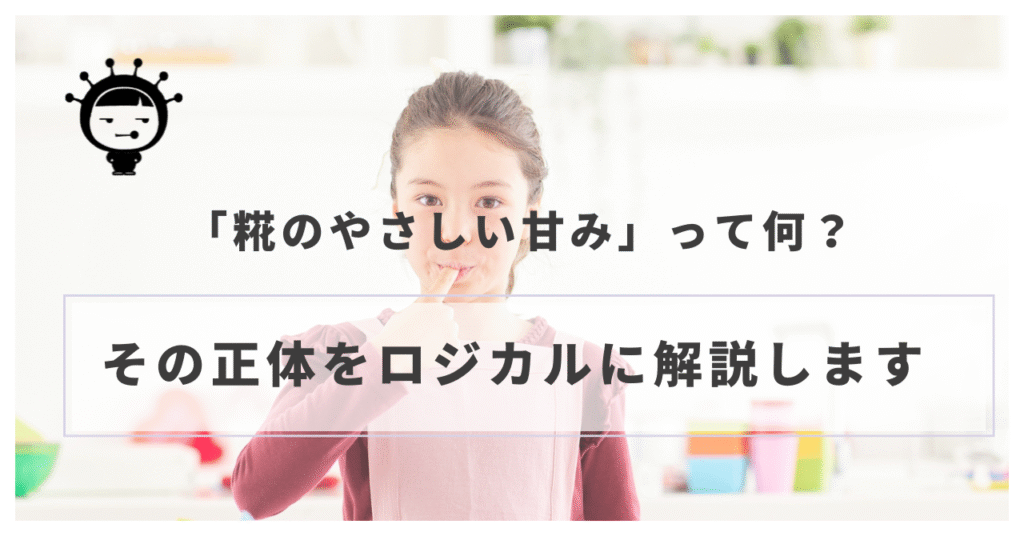
こんにちは。 モリゼ代表の酒師です。
糀を使った食品の紹介で、「糀ならではの、やさしい甘み」という言葉をよく見かけませんか?
「なんだか曖昧でよく分からないな」 「砂糖と比べて、本当にそんなに違うの?」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、そんな「糀のやさしい甘み」の正体を、少し科学的な視点から、分かりやすくロジカルに解き明かします。
まずは砂糖の甘さを知る
糀の甘みを理解するために、まずは比較対象である砂糖について考えてみましょう。
私たちが普段使う白い砂糖(上白糖など)の主成分はショ糖という糖質です。ショ糖は、甘みの成分がギュッと凝縮された純粋な結晶のようなもの。だから、舌に乗せた瞬間に「ガツン!」とストレートで強い甘さを感じます。その甘さはシンプルで、後を引かずにスッと消えていくのが特徴です。
糀の甘みは「オーケストラ」のようなもの
一方、糀が生み出す甘みは、砂糖のような単一的なソロ演奏ではなく、さながら「オーケストラ」のような複雑で奥行きのある味わいです。つまりたくさんの種類の糖が合わさって「甘み」を作るのです。
その理由は、糀が持つ「酵素」の働きにあります。糀の甘みは、お米のでんぷんが、麹菌の作り出すアミラーゼという酵素によって分解されることで生まれます。この過程で、砂糖の「ショ糖」とは異なる、複数の種類の糖が生まれるのです。
- ブドウ糖: すっきりとしたキレのある甘み
- オリゴ糖: 穏やかで、まろやかな甘みまた、糀の発酵で生まれるオリゴ糖は、さらに細かく見ると様々な種類があります。例えば、イソマルトオリゴ糖やマルトトリオースなどです。これらのオリゴ糖は消化されにくく、そのまま腸まで届いて善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える働きがあると言われています。
甘みだけじゃない!「旨み」が奥行きを生む
さらに、糀のすごいところは、甘みだけでなく「旨み」も同時に作り出している点です。
麹菌は、アミラーゼだけでなく、もう一つの重要な酵素プロテアーゼも生み出します。このプロテアーゼは、タンパク質を分解して、旨み成分である「アミノ酸」を作り出す働きを持っています。
つまり、糀の甘みの中には、
- 複数の糖が織りなす、複雑でやわらかな甘み
- アミノ酸がもたらす、豊かな旨みこの二つが共存しているのです。甘みと旨みが合わさることで、ただ甘いだけではない、味にぐっと深みと奥行きが生まれます。
糀シロップ コージローは「時間」をかけて甘みを引き出す
糀シロップ コージローでは、この酵素の力を最大限に引き出すために、とても長い時間をかけています。私たちは、90時間という時間をかけてじっくりと米麹を培養し、そこからさらに25時間かけてシロップを発酵させています。
なぜここまで時間をかけるのか。それは、甘みを生み出すアミラーゼなどの酵素に最大限に働いてもらうためです。時間をかけることで、お米が持つ本来の甘さを限界まで引き出すことができるのです。だから、砂糖を一切使わなくても、しっかりとした甘さとコクのある味わいが生まれます。
やさしい甘みの正体は「複雑さ」
「やさしい甘み」という言葉の裏には、
- 複数の糖が作り出す、複雑でまろやかな甘み
- アミノ酸が生み出す、味の奥行きとなる旨み
という、麹菌の酵素が生み出す仕組みがありました。
糀の甘みとしてよく言われる「やさしい甘み」は、決して曖昧な感覚的なものではありません。それは様々な成分が絶妙なバランスで組み合わさってできた、いわば発酵の芸術作品のようなものです。この複雑さこそが、私たちが「やさしい」と感じる甘みの正体なのです。
糀シロップコージローの「やさしい甘み」の中に広がる複雑な味わいを、ぜひ意識してみてください。
きっと、新しい発見があるはずです。